大大前提部分です。
この基本をわかっていない方って多そうです。
ルールの枝葉末節ばかりに目が行き、この根幹が頭の土台にはちゃんと入っていないから、
案件に対する苦労が、水の泡となってケースって、
実は意外とあるんじゃないかと。
なお、いつもながら、
偉そう言ってる私自身、こういうミスを過去にしてるから、
ダメだな~全然わかってなかった…って言ってるだけの事ですからね。汗
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
(在留資格の新規”許可申請”のガイドラインではありません)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
とはいえ、個別具体的に例示しないと、
不慣れな方は目にも入らず気にも止まらないと思われ、
いくつか、私の理解の範囲で、ガイドラインにあるポイント毎に列記してみます。
なお、全て対象は主に「外国人本人」のみならず「受入先」も当事者として該当します。
まずはガイドラインの前提。
「在留資格の変更及び在留期間の更新は、入管法により、法務大臣が適当と認めるに足りる“相当の理由”があるときに限り許可する」
「“相当の理由”があるか否かの判断は、法務大臣の自由な裁量に委ねられ、総合的に勘案しているが、この判断に当たっては、以下のような事項を考慮している」
つまり、以下のポイントを押さえない限り、
“在留資格の種別を問わず”、変更も更新も不許可になりますよって話です。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
→「必要な要件」として当たり前の話なので割愛。
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
→「原則として適合している」…つまり、例外もありうる要件。
上記2点よりも、以下が問題。
以下のポイントは、判断の代表的な考慮要素で、すべて該当する場合であっても、変更又は更新を許可しないこともある。
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
→不法就労はもちろん、職種(分野)不適合や、資格外活動を超える就労など、わかっていずとも隠れてされてたりしたらオシマイって話。
(みなし再入国でも長期間に渡るとダメな場合もある→いったん、在留を終えて、再度手続きを踏んで在留資格を取得しなさいって話)
4 素行が不良でないこと
→警察に逮捕されたり、入管に不法就労助長を疑われたり、反社会勢力であったり、これらも隠されてるとオシマイ。
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
→つまりは、安定所得の保証(見通し)がない限り、変更も許可もデキナイのは当たり前。足りる技能ってのは、主に変更にあたってかな。
6 雇用・労働条件が適正であること
→労基法や安衛法で違反があったり、主に受入側で注意すべきことですね。4日以上の出勤停止事故とか、リフトにライセンスなく乗せてたとか、賃金不払いがあったとか、この点はお分かりの方も多いかと。
7 納税義務等を履行していること
→社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災)や住民税、所得税などなど、受入側が隠れて未納であった場合も、ダメですね。
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
→ここが問題ですね…つまりは、各種届出や細かなルールを全て必要十分に対応できていないと、ダメになるって部分。
お分かりでしょうか…業者側が受入側の襟元を正せられない限り、
変更も更新も不許可にしますよ…不許可にできますよ…って話です。
登録日本語教員を捕まえなきゃ…とか、
日本語能力を担保できる送り出しを見つけなきゃ…とか、
検定の練習問題を見つけ出して対策してもらわなきゃ…とか、
月に一度は訪問しなきゃ…とか、
色々大事ですが、基本線の確認は、死活問題になるって話です。
つまるところ、
残念な受入先、残念な外国人を掴んでる先は、
そもそもが事業にはならないって話です。
たかだかA4で2ページ分です。
文字だけだから読まない…よりは、
プリントアウトして、理解する努力をするだけの意味はありますよ。
————————————————————–
*こんな私から様々な企画、案内が届きます。
フツー、一般的には流れない案内ばかりなので、オモロイっすよ。
メルマガ登録はコチラ。
自分で言うのもなんですが、”目覚めたい業界人”は、登録しとくと良いと思います。
————————————————————–

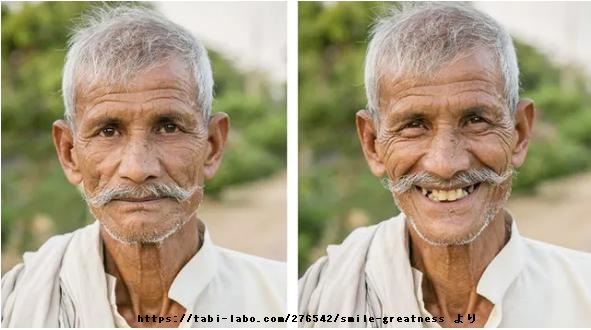

コメント